人間とくらす【馬と人との歴史】
明治・大正時代から敗戦まで
-

日本人が扱い易い多目的馬「日本釧路種」 -
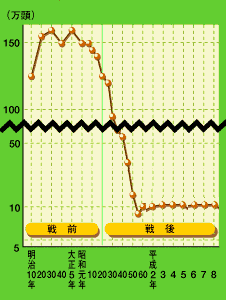
わが国における馬飼養頭数の変遷
国家的施策として初めて取り上げられた馬政計画
日清・日露の両戦争で初めて外国の改良種に対面した日本は、国内産馬が体格・資質の両面で改良種にはるかに劣っていることを痛感。そこで外国から改良種を導入し、国是として軍馬生産に取り組み(馬政計画1906年)、敗戦までに目を見張るような成果を挙げました。
1935年(昭和10年)までの30カ年を区切って実施された第一次馬政計画では、サラブレッド、アラブ、アングロ・アラブ、アングロ・ノルマン、トロッター、ハックニー、ペルシュロンなど、当時世界に名を馳せていた改良種の種雄馬を輸入し、国内産の雌馬との交配による産馬改良が精力的に実行されました。
第一次馬政計画の輝かしい成果
馬産地として北海道、東北、北関東、甲信越、九州・沖縄地方のほか、淡路、対馬などの島嶼(とうしょ)も加えた国家的・総合的な振興策が実施され、この指定は地域農業(とくに寒冷地に必須の有機質肥料である厩肥生産)の振興を考慮した、総合的な国家事業でした。
ペルシュロン種とアングロ・ノルマン種との交配によって改良された体高約148cmの日本釧路種(青毛)と、奏上釧路種(鹿毛)は、日本人青年男子の体格とうまくバランスがとれた多目的馬として、世界の注目を集めました。しかし、これらの馬は戦後には需要が無くなり、1951年の一千頭共進会を最後に姿を消しました。
■わが国における馬産関連事項の変遷
| 年次 | 主要事項 |
| 1872(明治5年) | 千葉県三里塚に種馬所、種羊所(下総御料牧場)を設置 |
| 1873( 6年) | 陸軍兵学校寮に「馬医生徒」15名を置き、フランス陸軍獣医の指導を受ける |
| 1875( 8年) | 札幌農学校(北大)で獣医学教育開始 |
| 1877( 10年) | 駒場農学校(東大)で獣医学教育開始 陸軍馬医学会創立 |
| 1882( 15年) | 陸軍獣医学会創立 |
| 1885( 18年) | 大日本獣医会(日本獣医学会)創立 |
| 1887( 20年) | 軍馬伝染病取扱規則制定 |
| 1890( 23年) | 獣医免許規則、蹄鉄工免許規則制定 |
| 1896( 29年) | 獣疫予防法制定 |
| 1897( 30年) | 海港検疫開始 |
| 1900( 33年) | 牛乳営業取締規則制定 |
| 1906( 39年) | 第一次馬政計画発足(外国種の導入による改良)、馬政局設置 |
| 1916(大正5年) | 馬匹去勢法施行、畜産試験場設置 |
| 1921( 10年) | 馬籍法制定、獣疫調査所(家畜衛生試験場)設置 |
| 1923( 12年) | 競馬法制定(勝馬投票券発売)、帝国競馬協会創立 |
| 1924( 13年) | 日本畜産学会創立 |
| 1932(昭和7年) | 日本釧路種成立 |
| 1936( 11年) | 第二次馬政計画発足(生産地域の指定) |
| 1937( 12年) | 奏上釧路種成立 |
| 1943( 18年) | 馬事研究所設置 |
