めん羊のからだのひみつ
からだの中はどうなってるの【からだの特徴】
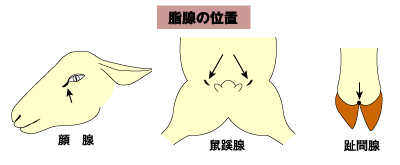
めん羊はウシ科
めん羊は偶蹄目(ぐうていもく)ウシ科に属する反すう動物であり、牛と同じように4つの胃を持ち、歯は下あごに8本の前歯(切歯)と、奥歯(臼歯=きゅうし)が上下合わせて24本、合計32本あります。体の基本的な構造は牛とほとんど変わりませんが、口の形状には特徴的な違いがあります。
牛の上唇は平らで分厚く、エサを食べるときにはあまり使いませんが、めん羊の場合は上唇溝と呼ばれる縦の溝によって上唇が左右に分かれており、これを器用に動かすことができます。このため、地面をはうような短い草や木の葉なども上手に食いちぎって食べることができます。
長い消化管
めん羊の消化管は「羊腸のごとく」と長いものの例えとして使われるように、他のウシ科の動物よりも腸が長いことが特徴です。小腸の長さは26-28m、大腸は6-8mと、体の大きさに比べて非常に長い腸を持っているため、消化・吸収能力に優れています。
この他、めん羊の特徴として体の3部位にある脂腺(しせん)があげられます。眼の下部にある顔腺(がんせん)、後肢の付け根にある鼠蹊腺(そけいせん)、四肢の蹄(ひづめ)の間にある趾間腺(しかんせん)です。これらの脂腺からは、特有の臭いがある物質が分泌されます。めん羊が群(むれ)で生活をするうえで、重要な働きをしているものと考えられています。
